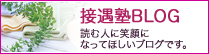固定電話恐怖症から少しステップアップ
2020/02/25
苦手意識を克服する方法
それは苦手分野で成功体験を作ること
電話応対が苦手な人が
ほんの一言でも誰かから褒められれば
す~と苦手意識から遠ざかることができます。
今日は
褒められやすい『言葉使い』
きれいな日本語を使うと褒められやすいです。
わかりました→承知いたしました
知っています→存じております
そうです→さようでございます
来ました→お見えになりました
お洋服→お召し物
お会いする→お目にかかる
他にも色々あります。
若い人ほどこういったきれいな日本語を使うと効果があります。
「若いのにきれいな言葉使いね」
きっと誰かからこんな誉め言葉をかけてもらえますよ。
状況に合わせてどんな言い回しをするのか
頭を悩ます場面もあるかと思いますが
まずは
ひと言から初めてみるのもいいですね。


固定電話恐怖症にならない方法4
2020/02/24
固定電話恐怖症にならない方法
恐怖症と自分が思い込む前に簡単な方法で
固定電話恐怖症から抜け出しましょう。
相手の言うことがうまく聞き取れない
取次ぎを言われたのに
相手の会社名、名前が聞き取れない・・どうしよう
何度も聞き直すと
失礼にならないか、機嫌が悪くならないか
と、色んなことを考えて応対がうまくできなくなります。
あやふやにするより
聞き直した方がいいです。
「恐れ入りますがもう一度お名前をお伺いしてよろしいでしょうか」
「申し訳ございません。もう一度お願いします」
クッション言葉を使いながら聞き直せば大丈夫です。
ここまでは
出来ている人が多いですよね。
それでも聞き取れないこともあります。
リラックスしていると聞き取れる名前も
緊張していると耳に入ってこないものです。
では今日のワンポイントアドバイス。
漢字を聞くといいです。
「恐れ入ります。どのような字をお書きになりますか」
誰しも人生でこんな質問を受けたことが何度もあります。
殆どの人が自分の名前を漢字で答えるパッケージを持っています。
自分の聴いた言葉のニュアンスと
漢字を組み合わせると
正しいお名前を聞きとることができます。
こうやって
少しずつ苦手意識から遠ざかっていきましょうね。


固定電話恐怖症にならない方法3
2020/02/23
仕事にストレスはつきもの
電話応対もそのうちのひとつ
恐怖症になる前に苦手意識を少なくする方法です。
今日は『声のトーン』です。
電話では声が相手に届く時、生の声よりもくぐもって聞こえます。
声が暗いと良い第一印象を与えることができず
相手まで愛想が悪くなってしまいます。
なぜなら
第一印象が相手の感情の行方を決めるからです。
電話をかけた相手が愛想が悪い、暗いと感じれば
不快感を感じた相手も愛想が悪くなっていきます。
電話応対が苦手な人にとって
相手の雰囲気はとても気になります。
なんか恐そうな人だと感じると
ますます緊張してきます。
せめて最初の挨拶だけでも
明るいトーンの声を出しましょう。
でも
それができないから悩んでいるんだ・・・という人も多いですよね。
では今日のワンポイントアドバイス。
アゴを上げて言ってみましょう。
自分が電話に出るときの姿勢を思い出してみてください。
自信のなさなのか
クセなのか
うつむき加減で言っていませんか。
挨拶の部分だけでも
アゴを上げて言ってみましょう。
いつもより明るい声が電波にのって相手様に届きます。
良い流れができます。


固定電話恐怖症にならない方法2
2020/02/22
”病名が付いた時から病気になっていく”
そんな言葉を聞いたことがあります。
固定電話恐怖所もそういった側面が大きいと考えます。
そう思い込む前に少しでもいい
抜け出してほしいと願っています。
今日は「準備」です。
電話応対が苦手とする方たちから
電話が鳴ると『焦る』といったことをよく聞きます。
『焦る』原因を簡単なところから探してみましょう。
●デスクが散らかっていてメモを置くスペースがない
●メモ帳がない
●筆記用具が見当たらない
●ボールペンが付かなくなった
●PCを立ち上げていないので質問に答えられない
もちろん、これ以外にも相手の話が聞き取れない
話の内容が切り分けれない・・・などありますが
それはおいておいて
簡単に『焦る』を解消できることからやってみましょう。
今日のワンポイントアドバイスは
「準備」です。
必要なものは手を伸ばせば届くところに置いておくことから初めて見てください。
そして
デスクの上をきちんと片付けておくことも大事です。
不要なものは紙切れ1枚でも処分しておきましょう。
昔と違いPCがデスクの上にドンと陣取っています。
メモを置くスペースも少ないです。
使うたびにあちらこちらに動かしていては
必要な時に焦って探すことになります。
探しているうちに相手様の言ったことを聞き逃し
負のスパイラルに入っていきます。
『焦る』原因をとりのぞくと
幾分か落ち着きが戻ってきます。
メモや筆記用具の定位置を決めておくことも
固定電話恐怖症から遠ざかる大事な『準備』です。
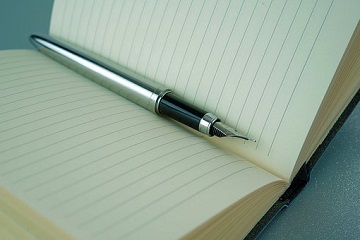

固定電話恐怖症から少しづつ遠ざかる方法
2020/02/21
固定電話恐怖症から少しづつ遠ざかる方法
効果が得られた体験をもとにお伝えします。
昨日は姿勢でした。
今回は『深呼吸』です。
固定電話が鳴ると「ドキン」となる心臓。
そのままで出てしまうと緊張が相手に伝わってしまいます。
相手に伝わるのはいいとして
それよりも影響があるのは自分が「緊張」を自覚してしまうこと。
~緊張してる、緊張してる、どうしよう・・・~
そのまま応対を続けると
相手の言っている内容が聞き取れない
声も上ずったまま
ますます緊張度合いが増してしまいます。
それが続くと自分は「固定電話恐怖症」だと思い込まざるをえなくなります。
やがて本当に固定電話恐怖症になっていきます。
では
今日のワンポイントアドバイス。
電話に出る前に1回でもいい
深呼吸をしてみてください。
出来れば深く
「ドキン」となった心臓の鼓動が少し落ち着き
安定した声と思考を取り戻せます。
いつもより落ち着て電話応対ができたとわずかでも感じれば
固定電話恐怖症から遠ざかったということです。
たとえそれが1ミリの距離であったとしても
固定電話恐怖症から遠ざかった証拠です。


固定電話恐怖症にならない方法
2020/02/20
固定電話恐怖症の人が増えているようです。
固定電話恐怖症にならないためには
自分もそうだと思わないことです。
その症状を自覚したところから
本当に「固定電話恐怖症」になっていくと
私は考えます。
そうなる前に抜け出してほしいと切に願います。
心理カウンセラーの先生も色んな手法で改善を促してくれると思いますが
私は私の立場でお伝えできることを書いていきます。
まずは
あなたは100%電話が苦手ではないことに気づいてほしい。
「知らない相手だと緊張する」
「周りの人に聞かれていると思うとうまく話せない」
「知らない業務内容を聞かれると頭が真っ白になる」
「周りがし~んとしていると言葉が出てこなくなる」
接遇塾のセミナーに来てくださる方の中には
こういった意見が多く聞かれます。
出来ないことにフォーカスしすぎて
ますます苦手意識をつくってしまっています。
100%出来ていないのではないことに気づいてください。
「知っている人だと安心して話せる」
「周りに誰もいなければリラックスして応対できる」
「業務内容がわかれば問題ない」
「周りがざわざわしていれば落ち着いて話せる」
そう
電話応対がうまくできるときがあるのです。
それも一度ではなく何度もあるのです
そこにフォーカスしてみてください。
そして
今日のワンポイントアドバイス
電話に出る前に背筋を伸ばして
胸を張って(鎖骨を前に出すイメージ)受話器をとってみてください。
これまでのあなたよりは
自信をもって電話に出ることができます。
なぜなら
その姿勢はあなたに自信と勇気を与える形だからです。


張り紙の文章で分かる接客のレベル
2020/02/05
修善寺にある高級旅館。
以前、こちらの本部の指導員2名様がセミナーに来てくださいました。
リゾートホテルに注力していくにあたり
マニュアル整備と指導を学ぶためでした。
さすが高級旅館、入口を入ったところから丁寧なご案内が続きます。
目の行くところどころに、さりげなく季節の小物が置かれています。
何より感動したのが
張り紙の文言ですね。
禁止用語や否定語は避けてください・・・といつもセミナーではお伝えしています。
内容を伝えるためには
「トイレットペーパー以外は流さないでください」
「部屋着で館内を歩かないでください」
など否定形でなくても伝えることはできます。
内容を伝えることが第一目的ですが
それを見たときにお客様が「どう思うか」が大事です。
お客様の心情に配慮してポスター、注意事項のお願いなどをしていますか。
張り紙の文言まで配慮のある言葉で書かれているところは
間違いなく接客・接遇のレベルは高いです。
こちらの旅館も色んな所にPOPや張り紙があります。
そのすべてがしっかり配慮のある言葉で書かれています。
お客様は気づかないかもしれませんが
小さな小さな心遣いです。
それが大きな企業の発展につながります。
本館の隣には
新館に次ぐ新館が建設されていました。

修善寺の豆まきでの戦利品

修善寺の梅

想像力からの声掛け ミスドの店員さん
2020/01/27
19日から連続5日間の企業様研修が無事に終わりました。
そして今は4日間連続のセミナー中。
毎日が真剣勝負の連続です。
企業研修の移動で立ち寄った佐賀駅構内にあるミスド。
ご存知のようにトレーを持ち流れ作業のようにレジまで進むのですが
私の前のお客様はドーナツを選ぶのに時間がかかっています。
私の後ろにもお客様
後にも先にも進むことができなくなりました。
トレーにはポンデリングが1個だけ・・・。
まあ、いいか・・・と思い前の方を通り越しレジに行きました。
「私がお取りしましょうか」
にっこり、こっそり店員さんが声をかけてくれました。
欲しい商品が前のお客様いるため取れなかったのだと思ってくれたようです。
「あっ、でも大丈夫です」
「では、飲茶などもございます。いかがでしょうか」
スーツケースを持ちスーツ姿の私を見て
きっと店内で食事をするのだと想像したのでしょうね。
その割にはポンデリングひとつ・・・。
十分に商品を選べなかったのだと判断し声をかけてくれたのです。
接客には「想像力」「洞察力」が欠かせません。
何も考えないと
「店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですか」
といったマニュアル言葉しか出てきません。
いかにマニュアルを超えた応対ができるかが
接客の醍醐味でもあるのです。
もちらん、私は飲茶をおいしくいただきました。

お奨めのスタートライン
2020/01/20
テレビのリモコンを買いに秋葉原に行きました。
頭がクラクラしてきました。
リモコンと言えども種類が多いですね。
まあ、メーカーがたくさんあるから仕方ないですね。
何を買えば良いかわからず店員さんに尋ねました。
親切に対応してくれたので
素直にお奨めのリモコンに決めました。
対応してくれた店員さんにお礼を言ってレジに並びました。
会計が終わり振り向くと先ほどの店員さん
「もし御用の際はよろしくお願いします」
と、名刺を渡してくれました。
「はい、ありがとうございます」
と言って名刺をよく見ると
『docomo』と書いてあります。
「え、docomoの方だったんですか」
なんとdocomoのスタッフさんだったのですね。
docomoは高いので20年近く使ってたけどほかのメーカーに変えていた私。
後2か月で2年縛りが終わります。
またdocomoも選択肢に入れようかなと
リモコンを眺めながら考えるのでした。
売上を上げるためにはお奨め欠かせません。
そのお奨めをいつするのか
店に入ってきたとき
商品の前に立った時
商品を手に取ったとき
いえいえ
スタートラインはこんなふうに
もっと前にひかれている場合があります。

機械化が進むと接客のレベルが落ちる
2020/01/12
カジュアル洋品で世界的に有名なチェーン店。
最近はセルフレジがほぼ全店に浸透しています。
人手不足、働き方改革もあり必要な措置です。
今日はヒートテックを買いに行きました・・・が、
いつの間にか
とても寂しい活気のない店になってしまっていました。
セルフレジで会計し店を出るとき
誰からも「ありがとうございます」がありません。
それだけではなく
セルフレジ付近ではスタッフの女性が一人
何か作業をしているのですが・・・作業が中心で周りを見ていません。
電話が鳴りましたが
誰も出ません。
乾いたコール音が鳴り続けています。
近くにいる女性スタッフは出る気が全くなさげに作業を続けています。
しばらくして男性スタッフが小走りでやってきました。
以前なら第一対応者がサポートに入り
更に必要な場合は第2対応者が・・・といった具合に
多くのスタッフさんがお客様に気を配るためのアンテナが働いていました。
その連携にしばらく様子を見ていたものでした。
有人レジの時は元気な挨拶と笑顔で
活気があり笑いがありました。
買い物をする楽しさがありました。
少なくとも「ありがとうございます」の声がお客様の背中を追いかけていました。
それが
全くなくなってしまっているのです。
セルフレジはお客様に気配りしなくてよいための機械ではなく
そのためにできた時間を接客に使うためのものです。
接客の時間を省いてしまうと
お客様は間違いなく離れていきます。