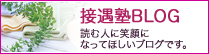「気を付けて」なのか「安心して」なのか
2023/01/20
伝え方によって気持ちのステートはずいぶん変わる。
レンタカーを借りた。
何を隠そう運転は大の苦手だ。
自分の車ならまだしもレンタカーとなると猶更だ。
おまけに良く知らない道を走るとなると緊張感しかない。
当然保険はnetで予約時に入っておいた。
ぶつけても事故があっても保証してくれる「ダブル」という保険だ。
車を借りる手続きの際スタッフの女性が
「保険はダブルで入っていただいておりますので
どうぞ安心して運転してください」
「気を付けて運転してください」と言われると
ドキッとし、ガチガチに緊張するものだが
「安心して」と言われると
リラックスして力を抜いて運転できる気がした。
言葉は事故をも減らすのかもしれない。
接遇研修では必ず伝えている内容だが
言葉を慎重に選ぶ必要性を改めて感じた。

接遇研修はユニフォーム着用で
2023/01/19
本日は姫路の企業様で研修だった。
やはり現場に近い研修は身が引き締まる。
研修をする際は現場に近い状態が最適だと思っている。
場所は勿論だが難しいなら
ユニフォームだけでもを着用してもらうと良い。
ユニフォームが難しいなら
髪型だけでもまとめてもらう。
これはオンラインであっても同じだ。
可能な限り現場に近づけると効果は大きい。
よそ行きの格好だと現場に戻った途端現実に引き戻される。
これは私の経験からの実感だ。
よそ行きの場所、よそ行きの服、よそ行きの言葉
職場に戻った途端すっかり元に戻っていた
本日は現場直結
研修前後には社長や幹部の方と打ち合わせもさせていただき
やはり現場はいいなぁと気分が若返った気がした一日だった。

写真は今日の富士山

地域に合った商品開発が絶対必要
2023/01/18
同じ業種でも地域によって売るものが違う。
昨日は埼玉の企業様で研修だった。
その前は宮崎。
どちらも同じ業種だ。
片方はアップセルで売り上げを上げていく。
ところがもう片方はダウンセルで客数を確保する。
これはそれぞれのオーナーの方針ではなく
地域性が大きく関連している。
顧客層は全く同じ。
地域の客数と環境の違いだ。
戦略や戦術を考える際にここを読み間違えると大きな打撃を受ける。
チェーン店であってもこれは同じだ。
全く同じ商品を提供すると必ず失敗する。
店舗のある地域を良く知ることが大事だ。
宮﨑も埼玉
双方とも見事にはまって増益を繰り返している。
接遇研修を担当する私は
それぞれの企業様にあったアップセル、ダウンセルの手法をお伝えする。

とっさの言い換えはさすがである
2023/01/17
自宅でいるときは首にタオルを巻く。
出張の際に買った「クマもん」の柄だ。
首に巻くと肌触りが良く暖かい。
先日、美容院に行くことになっていた。
美容院は首回りが空いた物を着ていかないと都合が悪い。
出かけるまでタオルを巻いて寒さをしのぐ。
美容院へ付いて
「コートとバッグをお預かりします」と言われ渡す。
「マフラーもお預かりします」
マフラー?そんなものは巻いた覚えはない。
しまった!
くまモンタオルを巻いたままだった。
恥ずかしいと思いながら慌てて外す。
それにしても
美容師さんの気遣いはさすがである。
どこからどう見ても タオル もしくは 手ぬぐい デアル。
それをとっさに「マフラー」と言ってくれた。
さすがである。

2月3月セミナー募集中です
2023/01/16
2月3月接遇セミナーと電話応対セミナー
募集を開始しました。
予定がなかなか読みづらく久々の開催となります。
接遇セミナーは医療・介護の現場で働く人のセミナーです。
少人数制ですので参加者の方の
状況やご質問を受けながら実施しております。
説明の仕方、コミュニケーション、
電話応対、NLP理論に基づく感情の整え方など
患者様、利用者様に対してだけでなく
働く仲間同士の関係性も良くなる内容のセミナーです。
是非、ご興味のある方はご検討ください。
*医療・介護以外の接遇セミナーは現在調整中です。
お急ぎご希望の方はマンツーマンセミナーも承っております。

真剣さを取り戻す第8波
2023/01/15
コロナ蔓延の第8波において
危機管理を学んだ。
「できているつもりだった」
「慣れが出てきていた」
「知識はあったのにいざとなるとできなかった」
接遇研修でも色んな意見が出てきた。
正直な感想だと思う。
店舗の入り口に置いてあるアルコールも
真剣にやっている人は少なくなった。
「ポンプ式は下まで押し切ること」
現場で働く看護師さんの言葉だ。
「体調異常があれば数回、高原検査をする」
職場でクラスターが起こった職員さんの言葉。
「予防のためにやっていることも
なぜそれをやっているのか意味を知ること」
研修では実際に大変な思いをされたが故に学んだ事柄が話し合われた。

絵文字OKと私は思う
2023/01/14
本日はLINEの活用とアップセリングの研修だった。
若い人でもしっかりとした文章を書くことに感動した。
思いやりの言葉がキチンと書かれている。
受け取ったお客様の笑顔、安心感、親近感が見えるようだ。
接遇研修では絵文字OKと指導をしている。
勿論、ハートが飛び交っていたりふざけた絵文字はNGだが
コミュニケーションツールとしては
絵文字しかない。
「丁寧さに欠ける」とおしかりを受けることもあるかもしれない。
しかし
プラス効果の方が大きいと私は考える。
少数のNG意見に左右されて
大きいな効果があるものを使用しないのはもったいない。
全員100%喜んでくれるものは難しい。
コミュニケーションにおいては特にだ。
「賛否」あるものは「否」を0にするのではなく
「賛」の効果がどれだけあるかを考えて
恐れず取り組むべきだと
私は思うがいかがだろうか。

セールストークよりも雑談
2023/01/13
「お客様、キラキラきれいですね」
呉服屋さんを除いていたら店員さんに声をかけられた。
もちろん私がキラキラしているわけではない。
スワロフスキーでできた眼鏡チェーンを褒めてくれたのだ。
それから、しばし立ち話。
数分後には足袋ソックス6足を購入していた。
店員さんはいきなりお奨めに入ったわけではなく
雑談をしただけだった。
こっちが勝手に
「何か買ってあげたい」という気持ちになったのだ。
接遇研修ではお奨めの練習で「雑談」を取り入れている。
いきなりお奨めをされると
どうやって逃げようか思考は逃げる方に働き始める。
しかし
雑談だとすんなり店員さんの土俵に乗ってしまう。
楽しい気分で買ったものは例え衝動買いでも後悔はしない。
手に入れた足袋ソックスも
今回の出張で活躍してくれている。

リカバリー力が接遇力
2023/01/12
今朝の羽田、思っていたより空いていた。
機体が動き出したのも定刻。
幸先が良い。
本日の企業様は少し後戻りした内容でお伝えした。
意外と取りこぼしに気づくものだ。
出来ていると思っていても実は体得までは至っていない。
体得していなくても
受講者様からはなかなか言い出しにくい。
一方、しっかり身に付いている出来事
記憶にとどめていてくれていることも確認できる。
改善点が発覚したら
改善方法が身に付いているというのが今回の収穫でもある。
色んな方面から意見が出てくる。
全員から出てくる。
自力で傷を防げる力が付いているということだ。
本人たちに自覚はないかもしれないが
このリカバリー力が
実は
チーム力であり接遇力である。

そこまでするか身だしなみ
2023/01/11
身だしなみは接遇においても基本中の基本。
人は動くものを見るので
指先や靴、これは気を付けなければいけない。
爪は白い部分が1ミリ以下になるようにカットする。
深爪の方もいるので手のひら側から見て白い部分が見えないぐらいでも良い。
5日に1回チェックするとオールOK。
最近は身だしなみも基準が緩やかなので
マニキュアはOKといった職場が多い。
カラーは職種によりOK範囲が異なる。
ピンク、ベージュ系であれば無難。
磨くだけで爪はずいぶんつやつやになって清潔感が増す。
私はコーティング?艶出し用の透明の物を付けていた時期がある。
怪我、肌荒れの方も身だしなみの観点からは
しっかりケアをしておくことが大事だ。
カットバンなんかは黒ずむのでポッケに替えを用意するように。
そこまでするか・・・と思われるかもしれないが
これぐらいでいいか・・・との差は大きい。