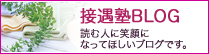限界突破
2023/12/01
一昨日は受付の方々の研修だった。
研修というより、現場を見て改善点を見つけるといった内容だ。
無い。
改善点がほとんど無い。
電話応対の肝である挨拶はハキハキ、笑顔でだけでなく
温もりを感じる素晴らしいものだ。
お客様に対しての目配りも声掛けも良くできている。
小姑根性、粗さがしさながら改善点を探す。
言葉使いはご本人に直接伝える。
即座に改善してくれる。
それだけポテンシャルが高い。
その他、いくつか気づいたことを幹部の方に報告する。
ここの企業様のすごいところは
次月は確実に改善を完了している行動力だ。
しかし
サービスに頂点は無い。
私の課題は
更なる高みを提案できるよう感性を磨くことだ。

写真は、鹿児島空港のツリーです。

早めの手を打つ
2023/11/30
一昨日はコールセンターの研修だった。
メキメキと実力を付けてきているメンバーだ。
とはいえ
社会もめまぐるしく変化する。
快進撃を続けていた数字が鈍ってきた。
様子を見るべきか手を打つのが先か
僅かなことでも手を打ってみることにした。
お奨めを紹介する順番を変えることにしてみた。
効果のほどは時を経ないとわからない。
「こうかもしれない」と思うことがあれば
やってみることが大事だ。
違っていれば、また考えれば良い。
私の仕事は知識を増やし
講じる策を蓄えておくことだ。
ということで、昨日も大量に本を購入。
偏らず多岐にわたり仕入れてみた。

急カーブでの進化
2023/11/27
昨日は介護施設での研修だった。
こちらの施設は驚くほどの進化を遂げている。
利用者様も続々と増え続けている。
利用者様にお話を伺っても不満など聞くことはない
「ここは皆やさしい」
「ここにくると楽しい」
「みんなに宣伝してるのよ」
などお褒めの言葉だけではなく
利用者様がスタッフにハグしたり
「あなたに会いたにきているのよ」
と声をかけてくれている。
もちろん、最初からこういった雰囲気だったわけではない。
進んでは止まり、止まっては進みを繰り返した。
オペレーションを変えた。
体操も工夫した。
作業効率を上げるためワークスケジュールも変えた。
施設を良くするためにはと皆が努力した。
最近は問題が起こるとすぐに責任者から
研修内容の要望が送られてくる。
とにかくやってみること。
動きながら考えること。
これが大事だ。
ふと気づくと閾値を超え急カーブで進歩している。

写真は施設のスタッフの方からいただいたお手製の梅干し
なんと、黒酢入りだそうです。感謝。

すぐやる!
2023/11/26
昨日は企業様研修だった。
受付スタッフでありながら営業の要素もある方々。
恐らく営業の意識はないのかもしれない。
にもかかわらず、手法を次々身に付け成果を出してくれている。
素晴らしい数字をたたき出している彼女に聞いてみた。
どういったところを工夫しているのか。
「すぐやることです」
即答だった。
人間の思考はネガティブに働く傾向にある。
そういった
思考のプロセスが入り込む隙がないくらいに
「すぐやる」
素晴らしい考えだ。
そう言えば彼女が
後追い営業の電話をかけていたところに出くわしたことがある。
反響営業ならまだしも
反応のないお客様への後追いはプレッシャーがかかる。
「本当は苦手ですけど、
『よし、今日はお天気も良いし頑張ろう!』と思ってかけました」
そう、彼女は
自らを「すぐやる」気持ちにさせるコツまでマスターしている。

利益体質の姿
2023/11/25
昨日は埼玉の企業様で研修だった。
受講者様を選抜し3回コースで終了とする研修に加え
幹部の皆様に
「パワハラ」「Z世代のトリセツ」として研修を実施
非常に熱心な企業様で利益は業界でも日本一と言われている。
施設内はいつ伺ってもお客様で一杯だ。
とにかく無駄がない。
かといって殺伐としているかというと
施設内はディスプレイ満載
どこを見ても楽しさが溢れている。
そして、いつも感心するのが
専務さんが良く動くことだ。
まるで時空をワープするように動いている。
利益を出す最大の方法は
コストカッターではなく
自ら良く動くTOPの姿を見せることかもしれない。

ロープレ
2023/11/22
昨日もZoomでの研修ご依頼だった。
佐賀の2拠点とつなぎ「お奨めの仕方」の研修だ。
場面を想定しロープレを実施する。
以前はスクリプト無しでやることが多かったが
最近は、簡単なスクリプトを必ず準備する。
スクリプト通りだと型にはまったセールスしかできないのでは
そう思われる方もいるだろう。
しかし
慣れてきたら、皆さんそこに肉付けしながら話してくれる。
そこに個性が発揮されるのだ。
その肉付けされた部分が
素晴らしく効果的なトークも多い。
なぜ「素晴らしく効果的」なのか
行動経済学を応用し解説しながら誉める。
ロープレを繰り返すほど
「素晴らしく効果的」なトークは増えていく。

Zoom
2023/11/19
昨日はZoomでの研修ご依頼だった。
70名ほどの皆様がご参加。
研修内容の半分は「クレーム対応」だ。
クレーム対応は理屈ではわかっていても
なかなか、現実は教科書通りにならない。
会社員時代は山のようにクレーム対応をしてきた。
台本通りにはいかない経験がほとんどだ。
謝罪の言葉をいくつも知ってはいても
口をついて出てくる言葉は
「申し訳ございません」の一択だ。
それでもほとんどのお客様は納得してくれた。
しかし
本当の意味で許してはくれていない。
クレーム対応で大事なのはそれから後だ。
同じクレームを出さないように改善をすること。
自分がクレームを言ったことで改善がなされた姿をみて
初めて本当に許される。

迷鉄
2023/11/16
姫路から次のご依頼先、名古屋に向かう。
現地へは名鉄に乗り換える。
「名鉄は『迷鉄』と言われているくらいわかりにくいです」
と聞いた通り、何度来てもわからない。
1番線といっても長~いホームで停車位置がいくつもある。
ホームには色を変えて線引きをしてあるが
慣れていない私はまるで分らない。
「○○行きは紫色のところに・・・」
紫?
そんな色はどこにもない。
赤ならある。
ホームに立っている駅員さんに聞いてみた。
「赤い線のところです」
「ここの赤ではなく後ろの方の赤です」
以前、アナウンスは「紫色の・・・」を繰り返している。
元来、色分けは分かり易くするものだ。
なぜ「紫」と言っているのか。
紫と言い切るなら足元の線も紫にしてほしい。
と、心の中で思っているのは私だけか
皆、整然と正しい位置に並んでいる。
迷わせるように作られているホームに慣れるには
学習が必要のようだ。

写真は、名古屋駅前のツリーです。

車内販売
2023/11/13
姫路の企業様へ研修に向かう。
新幹線の車内販売が無くなって初だ。
車内販売は
確かに利用する人が少なかった。
駅のコンビニやお弁当屋さんの長蛇の列をみると
購入後に乗車する人がほとんどだろう。
人々の動向を考えると無くす選択も致し方ないと思う。
こうやって考えると不要なサービスは結構ある。
いや、
「不要」といってよいのかわからないが
最近は買い物に行っても
ホテルにチェックインしても一言もしゃべらなくてよい。
レストランで食事をオーダーする際も自分のスマホで済む。
しかも
だからといって特に困らない。
まだまだサービスはスリム化が進むのだろう。

写真は、新幹線車内でQRコードでオーダーしたコーヒーとおまけのクッキー

シンプルサービス
2023/11/09
ご新規のご依頼で福岡に来ている。
泊まったホテルは今どきのスタイルだ。
部屋着、アメニティがないのはこれまでもあったが
フロントもない。
機械でチェックインし、振り向くとホテルのスタッフさんが立っていた。
ペットボトルの水をもらい簡単な説明を聞く。
ホテルの人と会うのはこれだけ。
快適だ。
部屋も至ってシンプル。
余分なものは一切ない。
快適だ。
人を介するサービスが手厚いほど高額になる。
そう、私たちはサービスにお金を払っている。
スマイルは無料ではない。
人的サービスを排するとリーズナブルになる。
部屋に鎮座していたアレクサのようなAIに話しかける。
「今日の天気は?」
これで十分事足りる。
ちなみにこのホテルは外国のお客様で一杯だった。